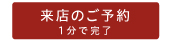二人の想いをカタチにする結婚指輪・婚約指輪。世界に1つだけをオーダーメイド。
婚約指輪と結婚指輪の意味の違いとは?
婚約指輪と結婚指輪の意味の違いとは?

婚約指輪と結婚指輪の2つにはどういう違いがあるのでしょうか。
今回は、婚約指輪と結婚指輪それぞれの意味合い、歴史を紹介します。
違いを知ることで、婚約指輪と結婚指輪に込めた意味合いを深めて指輪購入の参考にしてください。
目次
婚約指輪とは?

婚約指輪は、結婚の約束を交わした証しとして、男性がプロポーズ時に女性に贈るのが一般的です。婚約を公に宣言するという意味も含まれています。男性が女性に贈るという慣習は、多くの文化で見られ、その大部分では、婚約指輪は女性だけが着けます。 婚約指輪を婚約期間中だけ身につけるという厳格なルールは存在しません。実際、多くの女性は結婚後も婚約指輪を着け続けます。結婚指輪と婚約指輪は、しばしば同じ手の同じ指、通常は左手の薬指に重ねて着けられます。この習慣は地域や文化によりますが、2つのリングを一緒に着ける女性も多いです。
婚約指輪の歴史
婚約指輪の起源は、古代ローマ時代にまでさかのぼると言われています。約束を果たす誓いの証として、お互いに鉄の輪を贈っていました。現在のような指輪が用いられるようになったのは2世紀頃で、その頃は金の指輪がよく用いられていました。婚約指輪に宝石が使われるようになったのは中世初期で宝石が付いた指輪を贈るようになったそうです。
婚約指輪にダイヤモンドが飾られるようになったの15世紀頃といわれています。ダイヤモンドは美しい輝きを持つとともに、天然の鉱物の中では最も硬い物質で「不屈の精神、永遠の絆、約束」を示すといわれています。そのため、 男性と女性を結び付ける「永遠の愛のシンボル」として婚約指輪に装飾する宝石とされました。
しかしダイヤモンドを飾った婚約指輪は、王侯貴族など富裕な人々のものでしかありませんでした。19世紀末には南アフリカでダイヤモンドの鉱山が発見され、ダイヤモンドを安定的に供給できるようになったので、一般の人々にも広まってきました。
杢目金屋の婚約指輪(エンゲージリング)の一覧はこちらをご覧ください。»
結婚指輪とは?

一方の結婚指輪は、2人が結婚し「結婚の証」としておふたりそれぞれが身に着けるリングです。結婚式で通常交換され、その後も夫婦が一緒に生活する間中、身に着け続けることが一般的です。これは結婚の公的な証明としての役割を果たし、またその絆の持続を象徴します。
結婚指輪の歴史
古代ローマでは最初、鉄の指輪が結婚指輪として用いられ、結婚指輪の習慣が始まったのはもっと後、9世紀ごろローマ教皇であるニコラウス1世の結婚が由来とと言われています。花嫁に金の指輪、花婿に鉄の指輪を交換したとされています。この後に少しずつ結婚指輪の交換が広まっていき、13世紀には今と同じように男女間で結婚指輪を交換することが一般的となりました。結婚指輪が日本に伝わったのは、明治時代とされています。結婚指輪の慣習がきちんと定着したのは、大正時代になってからでした。
杢目金屋の結婚指輪(マリッジリング)の一覧はこちらをご覧ください。»
婚約指輪・結婚指輪をはめる指は?

婚約指輪や結婚指輪を左の薬指に着けるのは「左手は心臓とつながっている」という深い意味があり、現在の日本では、婚約指輪も結婚指輪と同じく左手の薬指に着けるのが一般的ですが、
文化や風習によっても変わってくるため、好きな指に着けたり、ネックレスにしたり好きな方法で身に着けて問題ありません。
杢目金屋の婚約ネックレス・ペンダントについてはこちらをご覧ください。»
婚約指輪・結婚指輪の価格相場は?

婚約指輪 は少し前までは「給料の3カ月分」というイメージが強かったですが、現代の相場は少し変わってきたようです。
杢目金屋の婚約指輪(エンゲージリング)の相場は約50万円前後とトレンドと同じぐらいです。 杢目金屋では相場と変わらない価格で「世界にひとつ」の婚約指輪をオーダーメイド可能です。 もちろん予算に応じて「さくらダイヤモンド」もお選びいただけます。
結婚指輪はシンプルなデザインが好まれているようです。
杢目金屋の結婚指輪(マリッジリング)の相場はペアで約50~55万円前後です。 木目金の結婚指輪の制作は素材選びから始まりますので、通常の鋳造の結婚指輪を作る何倍の手間がかかります。
木目金の色合い(金属素材の組合せ)、デザイン、内側金属、宝石アレンジ、刻印アレンジなどで「おふたりだけ」の想いのつまった一生ものの結婚指輪をオーダーメイド可能です。
「オーダーメイド・フルオーダーについて」はこちらをご覧ください。»